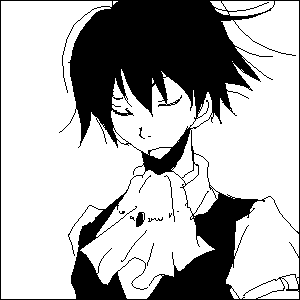ふるいこいのはなし。
2007/0908
witten by Miyabi KAWAMURA(KiraKira★Lovers)
special thanks ! Matsuri UME(Makesuta)
「……嫌だ」
細い身体が身じろぎ、オレの耳に掠れた、けれど断固とした声が届いた。
「嫌だ。どいて」
両肩を掴まれ、ぐ、と押し返される。
とはいっても、大人のオレと子供の彼の体格の差、では。そうされても殆ど意味は無くて、けれどオレは肘をつき身体を起こし、相手との間に僅かに隙を作ってやった。
「どうした、急に」
それまで大人しく口付けを受けていたくせに、覗き込んだ黒い目は、何故か不機嫌そうに顰められている。これといって思い当たる理由も無く、それまで頬を包んでいた掌で髪を撫でると、ぷい、と横を向かれてしまった。……それにつれて、さらりとした感触の黒い髪が流れ、首筋が露になる。
白いばかりの場所に残る、薄赤い痕。
先刻これを残したとき、彼はオレの下で、肌を震わせ背を心地良さそうに反らせていたのに、この変わり様は、一体何だ。
「顔も見せたくない位に、嫌?」
聞きながら顎を掴み、強いない程度の緩い力を篭める。こちらを向く様に促がすと、あっけない程簡単に、彼はオレを見返して来た。……来たのだが。
「さっきから何度も言ってると思うけれど」
真正面から視線を合わせ、しかし唇から漏れたのは、そんな可愛くないひとことだった。
「理由は?」
「そんなもの」
答えなければならない義務が僕にあるとでも、と、印象的な黒い目だけでそうオレに告げ、無意識に首を傾げる仕草。
口付けの余韻で色付いた眦と、薄らと上気している肌。そして、甘噛みを繰り返してやったせいで濡れて僅かに熟れている、薄い唇。……待ち侘びた逢瀬を半ばにされようとしているというのに、一瞬それらに目を奪われていた内に、彼は、覆い被さるオレの下から、するりと逃げ出してしまっていた。
「もう帰る」
ベッドの上に身体を起こした彼が、乱れきり、肩から滑り落ちていた白いシャツを羽織り直す。尖った肩甲骨が背に浮き、曲げた肘の頼りない位に細い造りが目について、オレも起き上がった。
手を伸ばし肩を掴み、後ろから抱き締める。
このまま何も無しに帰れると、オレが帰すと、彼は本気で思っているのだろうか。
「離して」
拒む言葉しか言わない相手の顎を、後ろから右手で掴み引き寄せた。耳殻に歯を立てきちりときつく噛んでから、細い首筋の線に唇を沿わせていく。
首元に口付けた途端、腕の中で相手の身体が大きく震えた。
「……っ……」
「……理由、は?」
答えないつもりなら、反応を返す場所だけに幾らでも何度でも痕を残してやるつもりで問いを繰り返し、相手の腰に回した腕に力を篭める。少年らしさを残した軽い身体を抱き竦め、しなやかな中にある固い骨張った感触すら愛しくて掌を這わせると、堪えられない、という風に、相手は息を詰まらせた。
「嫌、だって……言ッ……」
オレの腕を身体から剥がそうとしていた彼の左手が持ち上がり、自分の左肩に伏せられているオレの頭を抱え込む様に動いた。細い指が髪に絡み、ぎゅっと掴まれる。
……けれど、そんなことで逃がしてやる訳にはいかない。
首筋を噛みながら、顎を掴んでいた右手を薄い胸と腹に沿ってゆっくりと降ろしていく。
腰骨を掴み大腿に触れ、指を敏感な箇所に向かわせようとしたその時、ようやく、彼が強情な口を割った。
「かみ、……が」
「……髪?」
聞き返すと、頷いた彼が「離して」と呟いたので、腕の拘束を緩めてやった。
オレの腕から逃れ、少し離れた位置に座り直した彼の息はまだ乱れていて、こんな愛撫にも満たない接触にすら慣れていないらしい様子に、オレは苦笑した。
現当主を「初代」と称し、莫大な財力と強大な力を併せ持つファミリーとなったボンゴレの、この彼は、最強の守護者なのだ。
その戦う様を目の当たりにし、オレ自身何度も手合わせを繰り返して守護者選定の為に協力をしてはきたが、しかしそれでも。
彼が見せる思いがけない表情のひとつひとつを確かめ、新たに知っていく度に、オレの中で彼の存在は、更に大きく喪えないものになっていく。……腕に抱き、夜を共にする間柄になったとしても一向に思いは衰えず、例えば今の様に、互いの心がどこか読めず戸惑ったとしても、そんなことは何の妨げにもなりはしない。むしろ、彼が何を考え、何をオレに語ろうとしているのか、それを待つ僅かな時間にすら甘く焦らされるだけ、だった。
「――それで?」
ゆっくりと手を伸ばし、黒い髪に触れた。
長めに伸びたそれを梳く指は今度は拒まれず、心地良い手触りを楽しんでいたオレは、不覚にも次の彼のひとことで、動きを止まらされることになる。
「……あなたの髪が、顔と首にぶつかった」
今度は、オレが黙り込む番だった。
「それが……嫌、だったのか?」
「他人の髪が身体に触れるなんて、我慢出来ない」
言い切った彼は細い眉根を寄せていて、本気でそう思っているらしいことが感じられる。がしかし、聞かされた理由はオレを納得させるどころか、新たな疑問を増やしただけだった。
髪が駄目で、けれど、それなら。
……今まで、もう彼の口腔の湿りや熱を覚えてしまう位に繰り返してきた口付けは、嫌ではないのだろうか。
少し考え、オレは黒髪を弄っていた指を、彼の首の後ろに回した。
そっと引き寄せ仰のかせると、何をされようとしているのか理解したらしい相手が、目を閉じる。――口付けのときはそうするものだと彼に教えたのはオレで、幼い従順さに胸の内に甘い感情が滲むが、今は確かめるのが先、だった。
顔を傾け、唇を触れ合わせる。
彼のそれを食む様にしながら、舌先で隙間を探り、押しつける力を強くしていく。こつ、とわざと歯をぶつけ音を立てると、それに敏感に反応した相手の歯列に隙が出来た。
ぐ、と舌を、最奥まで飲み込ませる。
「! ……ンっ……」
びくりと震え後ろに引きかけた頭を、後頭部に当てた掌で阻む。
上顎と歯列の裏を探り、下顎の窪みに溜まった唾液を舌先で掻き混ぜてやると、ぬるく鈍い水音がたった。
彼の舌を絡めとり、表面を擦り合わせながら口付けの角度を変える。
小柄な相手に真上から噛み付くような角度に上向かせると、細い首が上下し、咽喉の奥に滴った二人分の唾液を、彼が嚥下したのが解った。けれど、それで終わりにはしない。柔らかくて小さい肉をゆるゆると噛みながら吸い上げ、完全にオレの口腔に迎え入れる。
自分の中を探られることに慣れ始めたばかりの彼は、自分の身体の一部が、他人の中に――濡れた熱い粘膜の中に入り込むことに関して、全く経験が無いらしい。戻ろうとする舌にオレは自分のそれをきつく絡めた。
歯列で挟み、ざらつく敏感な表面にわざと唾液を乗せてやる。二人の舌を重ね擦らせてそれを混ぜ、上手く出来たら甘く噛むことを繰り返した。……ん、と息継ぎすら覚束なくなった彼が呻いたのを合図に、ゆっくりと唇を離していく。
離れきる寸前、啼く様な吐息を漏らした相手の目は、潤みきっていた。
脱力しかけている身体を抱き寄せ、宥める様に背を撫ぜてやりながら、オレは口を開いた。
「口付けは、嫌じゃないのか?」
髪どころか、身体の内側の粘膜を探り合い、吐息も、そして唾液すら混ざる行為だというのに。
皆まで言わずとも、考えるところは伝わったのだろう。
オレの胸元に頬を預けたまま、彼が言葉を紡ぎ始めた。
「嫌じゃない。……だってこれは、全然違う」
「……違う?」
彼の言わんとするところを掴み切れなかったオレが、黙って背を撫ぜる行為を繰り返していると、オレに凭れていた身体を起こした彼に、名前を呼ばれた。
見下ろすと、真直ぐにオレを見上げる黒い目がそこには在った。
違うよ、と、もう一度そう言った相手の声が鼓膜を揺らす。
「偶然の接触なんて気持ち悪いだけで我慢出来ない。でも、あなたに触れるのは、僕が自分で決めたことだから」
だから、全然違う。
言葉と共に、伸ばされた細い白い指先が、オレの頬を掠め、髪に触れた。
首に回された腕。心地良い体重に引かれ身体が傾ぎ、引き寄せられた、と思ったときには、彼の唇がオレの肩に――肩に滑り落ちた金色の髪に、寄せられていた。
「だから、あなたの髪も、これなら嫌じゃない」
押し留めることの出来ない思いに引かれ、オレは彼の身体を、もう一度強く抱いた。
嫌じゃない、ではなくもっと確信のある言葉が本当はオレは彼から欲しくて、けれど今は、これだけで十分だった。
これから、全部伝えればいい。
思いの交わし方も、愛しさの伝え方も、これから全部、彼に教えていけばいい。
薄く色付いた耳元に唇を寄せ、好きだと告げる。
少しだけ、ほんの少しだけ、彼の背が応える様に震えた。
>>fin.
|