| イッコーモケイ(正式には一光模型)は、主にゴム動力をパワーソースとした年少者向けの動くプラモデルを発売していた会社です。後にアメリカンレコードカーの「ボンネビルレーサーシリーズ」をゼンマイ動力で模型化してヒットを飛ばした事もありましたが、ボックスアートやインストがポップでハイセンスな感じがあったものの一般的にはあまり強い印象のなかったメーカーかも知れません。しかしそのイッコーモケイが1960年代中期にエポックメイキングなキットをリリースします。それがこのクリヤータンクシリーズです。 実物を正確に縮小したミニチュアであるプラモデルが、その素材であるスチロール樹脂が本来持つ「無色透明」という性質を生かして他のマテリアルでは不可能なシースルーモデルというジャンルに至るのは自然の成り行きであったかもしれません。透明キットはアメリカではビジブルキット(あるいはビジブルモデル)と呼ばれていますが、1959年にモノグラムが出した「ファントム・ムスタング」をその嚆矢として、以後各社競って透明キットを自社のラインナップに加えて行きました。しかしレベルやマルサンの生物模型等極一部を除き、それらの殆どは航空機で占められていました。我国ではマルサン、田宮、コグレ、三共、長谷川、日模等がその戦列に加わったのです。そんな中で(現在当王国で確認されている中で)ただ一社このイッコーモケイだけが戦車をビジブルキットとして世に送り出したのでした。 これにはどんな理由があったのでしょうか。「ファントム・ムスタング」にインスパイアされ、その延長線上で戦闘機のビジブル化が突出したと見る向きもあるでしょうが、もう少し掘り下げてみると、そこに当時の日本のプラモデルが負っていた宿命のようなものが見えてきます。それは他ならぬ「動くプラモデル」という要請です。スナップやレベル(当時の呼び方では「ラベール」)のキットをコピーし、あるいは日本国内での代理販売契約を行っていたマルサンは、その商品展開の性格上プラモデルを最も欧米に近い感覚…即ち純粋な意味でのスケールモデルというスタンスで捕らえていたように思えます。しかし他の殆ど全てのメーカーは、如何にして魅力的な動くプラモデルを商品化するかという事に鎬を削っていたのです。その最右翼が戦車と自動車でした。特に無限軌道といううってつけのセールスポイントを持つ戦車は、先に述べたマルサンの「洋物キット」のラインナップを除いて殆ど全てが電動なりゼンマイなりあるいはゴムといった動力によって動くものでした。逆説的に言えば「戦車を動くプラモデルに仕立てた。」のではなく「動くプラモデルという商品コンセプトを具現化する 手段として戦車が選ばれた。」という事でしょう。 一方では飛行機も又モーターでプロペラを回転させる事が当たり前ではあったものの、モーターライズ化された飛行機が戦車と決定的に違うのは、それは単に動きのエッセンスを添加しただけであって、実機同様に空を飛べない以上はあくまでも鑑賞の対象でしかないという点です。鑑賞に重きを置かれた航空機は、その後更に純粋なミニチュアモデルとしての道を歩み、方や戦車はその後も長く「動くおもちゃ」として進化していく事になります。飛行機が鑑賞の為の模型であるという事は、如何に精密さを折りこむかという命題があり、それを突き詰めて行く先に内部構造の再現とその視覚化という要請から「透明キット化」に行きつくのは必然的なベクトルであったわけです。 他方で戦車はと言えば、透明化による内部構造の再現は即ディスプレイキットである事を意味し、それは又同時に動くおもちゃでなければならない当時の戦車プラモデルのレゾンデートル(存在理由)の否定に他なりません。「動く透明戦車」などというものは端から存在しえないのです。 そこでこのイッコーモケイというメーカーの特殊性が思い出されます。そもそもこのメーカーは戦車や飛行機や車の多くをゴム動力キットとして商品化しており、動くプラモデルのネームバリューという点では他社に大きく水を開けられています。自社以外の下請け、孫受けといった広いバックボーンを必要とする高度なモーターライズ商品の展開に不慣れであったろうこのメーカーは、発想の転換を図って動かないプラモデルの新しい市場を模索します。動かないプラモデルなら精密キットしかない。しかし飛行機のスケールモデルは既に群雄割拠の時代に突入しており、一方の人気アイテムである戦車もスケールモデルとしてはマルサンがアメリカにルーツを持つ太刀打ちの出来ない幅広いラインナップを固めている。ならばそこにもう一つ付加価値を高めるセールスポイントを入れなければならない。それがまだ何処のメーカーも手を染めていなかった「透明ディスプレイ戦車」となった事は想像に難くありません。そうして世に送り出されたのがこのクリヤータンクシリーズでした。 |
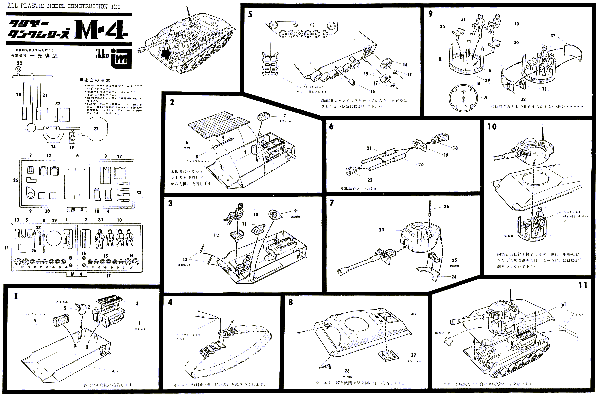 M−4のインスト。足回りでM−4の特徴ある懸架装置を全くオミットしている反面、砲塔内部には砲塔バスケットが再現されています。内部構造再現とはいうものの、実際はフィクションパーツが殆どで、現在の目でみるとかなり胡散臭い感じもしますが、一通り組み立ててみると中々味のある透明戦車が出来上がります。 |
赤いモールドのパーツ群は床板、座席、エンジン上面部品、砲弾等です。 パーツを包んでいるビニールは通常の柔らかいものではなく、チャラチャラとした硬質のものですが、そんな所もまた本キットの「クリヤーモデル」というコンセプトとマッチしてシャープな印象を受けます。 |
クリアー部品の全体像です。戦闘機のキャノピー等、当時のクリアーパーツは透明度が悪いキットが少なくありませんでしたが、このキットに限って言えば非常に繊細で美しい仕上りとなっています。バリすら殆どみられない成形は美麗の一言に尽きます。 |
キットのボックス、あるいはインストでは「M−4」としか記述してありませんが、エンジンルームの大型ルーバーからM4A3である事が見て取れます。 前述した足回りの表現の貧弱さに比べるとアンバランスな程、車体上面のディティール表現に力を注いでいます。 |
写真ではよくわからないかもしれませんが、コマンダーズキューポラの覗きガラスのモールドもしっかり入っています。このパーツにもバリは一切見られません。 |